
Dec 25, 2008
Dec 21, 2008
Dec 18, 2008
「1日30分」を続けなさい!人生勝利の勉強法55 古市幸雄

会社に入り、割とすぐに読んだ本。なので買ってからかなり間があるが、今でもパラパラと読み返す。
アマゾンやミクシィにレビューの多い本であり、評価は人によってかなりばらつきがある。1〜5星まで広く分布している。文中のどの部分に食いつくか人によって違うということと、その人が勉強や読書にどれほど免疫を持つかによって、本の内容を重く受け止めたり薄く感じたりするためと思われる。
自分がこの本に感じたのは、「卑近」な本だなぁという一言である。この本を読んだからといって、何か専門的な知識やビジネスの新常識が得られるわけではない。しかし、何かと面倒くさがり、時間管理などにおいて生活が崩れそうになった時、この本に書いてある「卑近」なテクニックが効く。だから、自分はこの本を「パラパラと」「何度も」読み返す。
役に立つ本であることは間違いない。
日々の生活で、自分のケツを叩いてくれる。
しかしこの本の内容そのものは、非常に薄い。
なので、「卑近」な本として紹介させていただく。
Dec 17, 2008
『ガラパゴス化する日本の製造業』 宮崎智彦

製造業を取り巻く環境が大きく変わっていることを証明し、(特に日本人に対し)現実を突きつけるために書かれたような本。野村証券で電電系企業分析・戦略分析を生業にする著者が書いている。
結論から言えば、「このままでは日本の総合電機は危ないよ、世界は大きく変わっているよ」ということである。根拠としては、中国、台湾、韓国がそれぞれの手法で日本の製造業にキャッチアップし、むしろ一部においては既に追い抜いていることを挙げている。
まず取り上げられているのは、「日本の市場は特殊なハイエンド市場であることを認識せよ」である。携帯電話やその他家電を始め、日本市場向けのものは機能的に高付加価値過ぎて他の国では価格的に敬遠されている現状を示している。この流れが続く中で、筆者は「日本はすでにガラパゴス諸島(のような特殊かつ限定的な生態系)になっている」と主張している。つまり、世界を相手に戦うパワー、免疫を失いつつあるということである。
主張されていることはまさにおっしゃる通りで、自分も家電を売る身として同じことを考える。「この機能はいったい誰が使うのか??」という疑問を自社製品に投げかけることは多いし、実際に自分が購入したもの(特に携帯電話)にも同じことを思う。
個人的には、日本人の「職人気質」が余分な形で発露した結果だと考えている。製品そのものの「高み」を目指すことに固執し、それを買う人間、使う人間を二の次にしてしまう。このような製品ばかり作る企業を、日本人よりも現実的で、したたかで、世界のマス市場を見据えている人々が支持するはずはない。この本を読むことでその考えを確かなものにした。
また、ビジネスの仕組みについても言及。日本の電機メーカーにありがちな、すべての工程を自社もしくは自社子会社で行う「垂直統合モデル」が限界に近づき、台湾企業とその顧客であるアメリカ系ファブレス企業を中心とした「水平分業型」モデルが猛威を振るっているとしている。
特にこの流れはモジュール型の製品(擦り合わせを必要とせず、パーツの組み合わせで機能する製品、パソコンなど)で大きな成果を上げているようである。また「後だしジャンケン」でコスト的アドバンテージを得やすい半導体や液晶パネルに関しても、日本企業の劣勢ぶりが浮き彫りになっている。
今までの収益モデルに依存していては、日本の総合電機メーカーに明日はない。世界を相手に戦わないとただ弱体化するのみ。それでもなお、日本市場を大事にし過ぎ、横との比較ばかりの日本企業(弊社も含め)が虚しい。
Dec 10, 2008
「マネジメント エッセンシャル版 基本と原則」P.F.ドラッカー
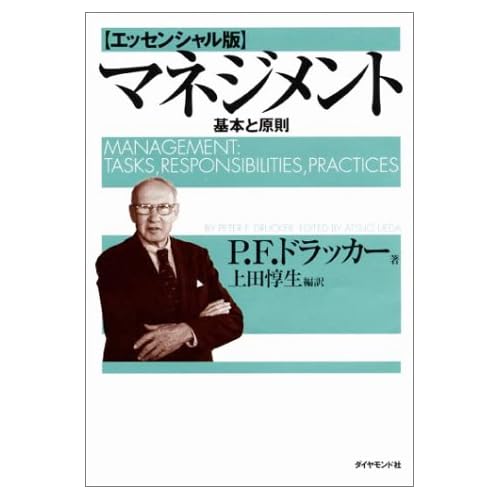
紹介するまでもない、「賢人」ドラッカーの著作を諸所抜粋したもの。長い時間をかけて、少しずつ読んできた。非常に密度の濃い内容・文体であるため、そこら辺のビジネス実用書のようなザックリした読み方ができない。
仕事、組織、マネジメント等様々な点について言及しているが、読んでいて個人的に著者の「気」を感じた部分を少し。
1 マネジメントは常に、現在と未来、短期と長期を見ていなければならない。
2 組織の目的は、凡人をして非凡なことを行わせることにある。
天才をあてにするな。
3 何が正しいかだけを考え、
誰が正しいかを考えない。
4 学ぶことのできない、
後天的に獲得することのできない、
始めから持っていなければならない資質がある。
才能ではない、真摯さである。
仕事のみでなく、「人生」に対する心構えが得られる。
Dec 1, 2008
『アイデアのつくり方』

『ザ・プロフィット』の中で紹介されていた、アイデアの醸成に関する本。ちょい大き目の手帳サイズで、本としては非常に小さく、薄い。でも中身は濃い。
アイデアという名の「世の中を変える、新しい組み合わせ」を生み出すのに法則やコツはあるのかな??という問いかけに、広告に携わってきた著者が答えていく内容。
まとめてしまうと、
1 豊富かつ正確な資料集め
2 ひとつひとつを調べる、理解する、加工する
3 意識的・無意識的問わず、いろいろ組み合わせる
4 完成したら、それを実行する、試してみる
である。
このように抜書きすると身も蓋もないが、実際はより含蓄に富んだ文章で書かれているので、読んでいるだけで「世の中は実はシンプルかも」と感じられる。
シンプルに考えるのは、アイデアを生み実行するための、最高の土台。(←これは自分の意見)
・・・でも、これと同じようなこと説いている本に自分は出会ったことが・・・外山滋比古『思考の整理学』の内容と、デジャヴしました。あくまでも自分の感想ですが。皆さんもぜひ。
Subscribe to:
Posts (Atom)








